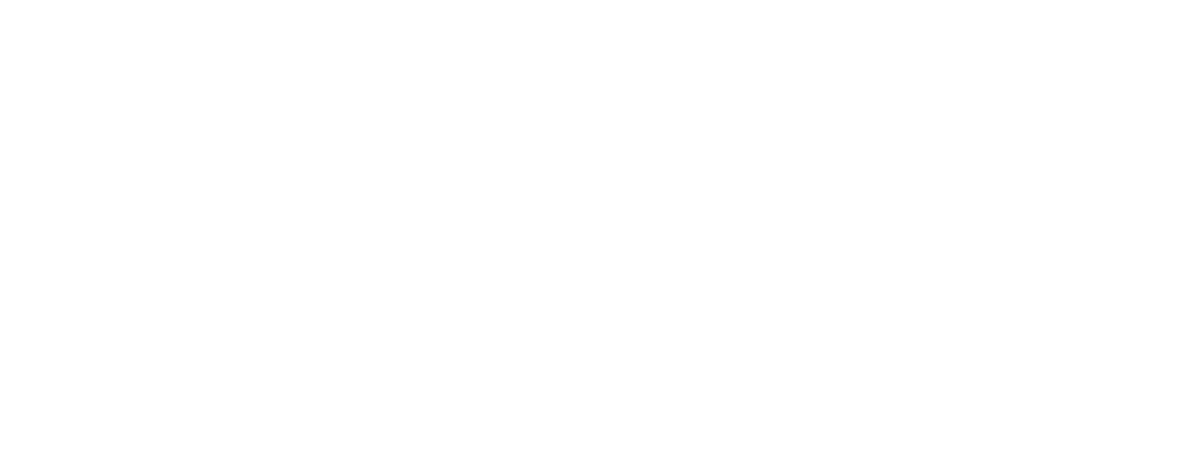SFFケース「NCASE M2」を使って、フルHDで高fpsを狙う小型ゲーミングPCを組んでいきます。
前回はパーツ構成を紹介しましたが、今回はビルド編ということで実際にパーツを組み込んでいきます。
NCASE M2は内部がまぁまぁタイトで、配線やパーツの取り付けにはそれなりに気を使う必要がありますが、そのぶん完成したときの満足感は非常に高いです。
実際の作業を振り返りつつ、注意したポイントや「ここはちょっと大変だったな」という部分もあわせて紹介していきます。
目次
マザーボードにCPU、メモリ、SSDを取り付ける

マザボにCPU、メモリ、SSDを取り付け。
ここに関して特筆するところはありませんね、向きに気をつけてやればOKです。
CPUクーラーを取り付ける

次にCPUクーラーを取り付けます。
簡易水冷の場合はケース内に組み込んでからでもいいですが、今回は D12L というそれなりに大きめな空冷クーラーなので、ケースにぶち込む前に取り付けちゃいます。
マザボ付属のSSDのヒートシンクがなくなっていますが、オープンフレームで動作確認したときにグラボが厚すぎてマザボのヒートシンクと干渉することが分かったためです…。
また、本来の取付方向と向きが逆になっていますが、I/Oポート側から吸気するのでこの向きが正しいです。
電源を搭載する
まず先に電源ユニットを組み込みます。

電源ユニットにブラケットを装着。向きに注意しましょう(1敗)

ケースのフロントパネルとマザーボードトレイを固定。

電源ユニットのファンが窒息しない向きで電源ユニットを取り付けます。
マザーボードを搭載する
マザーボードをケースに組み込みます。

マザーボードトレイにスペーサーを取り付けて、その上に乗せてネジ止めです。
この時点でCPU補助電源、マザーボードの電源、フロントパネルのケーブル、USBケーブルを接続してしまいます。
GPUを搭載する

GPUをマザーボードに取り付けます。
今回はライザーケーブルを使わず直接マザボに取り付けましたが、GPUを縦に設置する場合はそれ用のブラケットとライザーケーブルを使うことになります。
このときに、リアパネルも一緒に取り付けていきます。
ここでグラボの補助電源も接続します。

あとは残りのパネルを取り付けるだけなので配線の整理もしちゃいます。
残りのパネルを取り付けて完成

まずは、ボトムパネルを取り付けます。(写真は取り付け後)

サイドパネルを差し込み、その上からトップパネルをはめ込んでネジ止め。
これで完成です。SFFですが骨組みから組み立てる感じなので結構組みやすいな~と思いました。

パーツはこんな感じで詰まっています。でかいグラボが搭載可能なサイズになっているので、わりと何も無い空間がありますね。SFFはギチギチこそ至高!と思っている人は簡易水冷を使ったほうがいいかもですね。

パネルを閉じると内部は見えないので、パーツの見た目にもこだわっている人はサイドパネルをガラスにしましょう。僕は冷却性能を優先したのでこうなっています。
NCASE M2は組んでて楽しいSFFケース

というわけで、今回はNCASE M2を使った小型ゲーミングPCのビルド編として、組み立ての流れをまとめてみました。
でかいケースに比べてスペースに余裕がない分、配線やパーツの取り回しにはそれなりに気を使いますが、それも含めて「組んでる感」があって楽しいケースでした。物理的にパーツが干渉することもあるので、パーツ選びの段階から寸法はよく確認しておいた方が安心です。
SFFケースだと特に大きめのグラボや空冷クーラーを使う場合は、各パーツの余白を詰めて考える必要がありますが、今回のようにでかいグラボでも収まるのがNCASE M2のいいところだなと思います。
組んでみた満足感はかなり高め。SFFビルドに興味がある人には、NCASE M2 はマジでおすすめできるケースです。
→ ベンチマーク編はこちら
→ パーツ紹介編はこちら